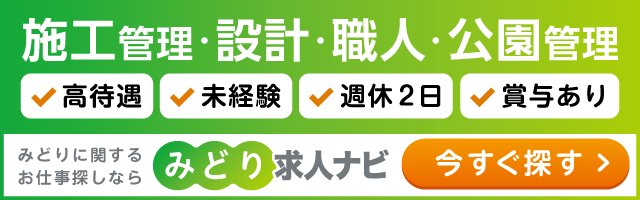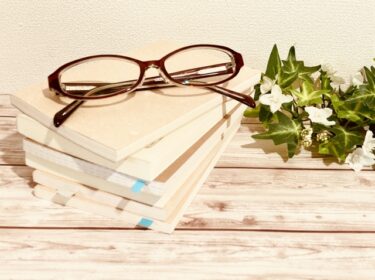造園業で働くために必須の学歴はありませんが、造園業に興味をもったとき、知識を得たり技術を身につけたりするために、学校で学んでみたいと考える人もいるでしょう。
高校や専門学校などでも造園学を学ぶことはできますが、より専門的かつ能動的に学ぶことができるのが、造園学を研究している大学の学部・学科です。
そこで本記事では造園学を学べる大学の学部・学科を紹介します。

造園学を学べる学部4選!
造園学を学べる大学から4校を厳選しました。学校の特徴、学部、学科、コース、研究室の詳細などについて、解説していきます。
東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科
東京農業大学は「実学主義」を掲げ、動植物全般を対象とする総合科学を扱う私立大学です。
6学部・23学科に分かれており、造園学を学べるのが、地域環境科学部の造園科学科です。
造園科学科では、自然と共生できる緑豊かな空間やガーデンデザインを考えるための知識、最新の技法、環境保全に取り組む上で重要な自然環境の回復や緑化技術などについて学べます。
また履修科目に応じて、測量士補、樹木医補、自然再生士補などの資格取得が可能です。
1、2年次は、造園科学概論、日本庭園論などの専門科目を履修しながら、製図の基礎を学んだり植物についての知識を深めたりする演習も受講します。
3年次には景観計画学、ランドスケープデザイン・情報学、造園植物・樹芸学、緑化植栽学、庭園技法材料学の5つある研究室に分かれ、より専門的な学習と研究、卒業論文作成に取り組みます。
卒業後は官公庁に所属して環境・緑化行政や都市計画・公園緑地行政に携わったり、造園、建設、土木会社などに所属し、緑やまちづくりに関する仕事に就いたりする人が中心です。
千葉大学 園芸学部 緑地環境学科
千葉大学園芸学部は、園芸学と造園学を専門的に学ぶことができる国立大学です。
園芸学部には4つの学科があり、造園学は「緑地環境学科」で学ぶことができます。
緑地環境学科はさらに、環境造園学プログラム、緑地科学プログラム、環境健康学プログラムの3つに分かれていて、主に2年次にプログラムを選択、3年次に指導教員の決定が行われます。
環境造園学プログラムは、緑に関わる環境やランドスケープの計画・技術、緑地科学プログラムは持続可能な社会の根底となる緑地環境の整備・管理・運営、道路・河川などの緑化と自然再生が、主な研究内容です。
環境健康学プログラムでは、園芸療法やアロマセラピーなど植物の療法的・福祉的利用、環境教育、医療福祉施設の緑化などについて学べます。
また所定の科目を履修して卒業すると、技術士補、樹木医補登録ランドスケープアーキテクト補などになることができます。
中学校理科、高等学校理科・農業のいずれかの教諭一種免許状の取得も可能です。
卒業後は国家・地方公務員の造園・環境分野の技術職、造園業のデザイナー、施工管理者、緑地環境の調査・計画・設計のコンサルタントなどとして活躍する人が多いです。
信州大学 農学部 森林・環境共生学コース
信州大学は長野県にある国立総合大学です。県内各地のさまざまな学部が点在していますが、農学部のキャンパスは上伊那郡南箕輪村にあります。
農学部にはさまざまな研究室がありますが、造園学を専門的に学ぶことができるのは、造園学研究室です。
複合的な視点から、地域、公園、緑地の計画とデザインについて学べるほか、防災・減災の視点から捉えた都市や地域の計画についての研究も行っています。
生物多様性の保全やそれに配慮した植生管理について学びたいときには、緑地生態学研究室を選択すると良いでしょう。
なお農学部は従来4つのコースに分けられていましたが、令和7年度からは3コースと1つの特別コースに再編成され、名称も変更されます。
造園学研究室、緑地生態学研究室はともに「山岳圏森林・環境共生学コース」に編成されています。
信州大学で造園学を学びたいときには、山岳圏森林・環境共生学コースを選択し、3年次の研究室配属で希望の研究室に入ると良いでしょう。
卒業後は林野庁や国土交通省などの関連省庁や、建設会社などで働く人が多く見受けられます。
南九州大学 環境園芸学部 環境園芸学科
南九州大学は宮崎県にある私立大学で、「食・緑・人」「いのちを学ぶ」をテーマとしています。
1967年に園芸学部園芸学科、造園学科の1学部2学科からスタートしましたが、現在では4学部4学科に再編成され、学部学科名も変更されています。
現在、主に造園学を学べるのは環境園芸学部・環境園芸学科です。
学科はさらに、3分野、5専攻に分けられて、造園学分野を研究しているのが、造園計画研究室、都市景観研究室、ランドスケープ研究室がある造園緑地専攻と、庭園デザイン研究室、園芸福祉研究室を有する花・ガーデニング専攻です。
造園緑地専攻では造園空間や緑地の設計、施工管理に関する技術が、花・ガーデニング専攻では生活環境を快適にする植物の癒やし効果について学べます。
所定の単位を取得すれば、学芸員、樹木医補、測量士補、理科や農業の中学校および高等学校教諭一種免許状の資格が得られます。
園芸環境学科では、人と自然が共存・共栄することの大切さを知り、緑や花の潤いと魅力あふれる都市環境・居住空間の創造することで、持続可能な社会を実現できる人材の育成を目的としています。
卒業後は「園芸」「造園」「自然環境」のスペシャリストとして、さまざまな行政機関や高等学校、中学校の理科・農業分野の教諭、造園・土木・建設会社、農業組合、公園協会などで活躍しています。

まとめ
造園学を学べる大学には「東京農業大学・地域環境科学部・造園科学科」「千葉大学・園芸学部・緑地環境学科」「信州大学・農学部・森林・環境共生学コース」「南九州大学・環境園芸学部・環境園芸学科」などがあります。
どの学科、コースもそれぞれ特徴があり、カリキュラムや研究内容が異なります。
造園学の中でもどんなことを専門的に学びたいのか、よく検討して選びましょう。